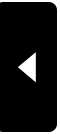2008年07月05日
密造酒
先日甘露梅の製造工程をお伝えしましたが、今回はその際に合わせて行った梅酒作りのお話でも。
梅を都合5kg購入したわけで、そのうち4kgは甘露梅を作成するために漬け込んだわけですが、残り1kgはどうしたのか?ついさっき書いたばかりですが梅酒にしてみました。
理由は簡単、甘露梅は完成(おいしく食べられる)までに1年以上の年月を要する為つまらないので、それまでの間楽しめるものはないかとなったところ、梅酒なら飲める様になるまでに3ヶ月程度と期間も短く待つのも耐えられるかなとかそんな理由。
作り方は途中まで甘露梅とほとんど同じ。梅を洗ってへたを取ってビンに詰め込みます。量もそのまま1kg。その後同じように蜂蜜1kを流し込み準備完了。

違うのは最後の行程だけで、りんご酢の変わりに果実酒用のブランデー1800ccを注ぎます。梅酒の定番ホワイトリカーじゃないのは雰囲気出す為とホワイトリカーじゃつまらないため。
当然蜂蜜とブランデーの層ができるのできちんと混ざるまでは定期的にビンをまわしてかき混ぜることを忘れないようにお願いします。
糖分1kgは甘くなりすぎるとの懸念がありますが、個人的に甘くないお酒がおいしいと感じられない(ビール、焼酎など)のでおそらく大丈夫でしょう!多分。3ヵ月後に乞うご期待!?
ぽちっと応援お願いします↓ランキング見てニヤニヤさせてください<ニヤニヤ?


梅を都合5kg購入したわけで、そのうち4kgは甘露梅を作成するために漬け込んだわけですが、残り1kgはどうしたのか?ついさっき書いたばかりですが梅酒にしてみました。

理由は簡単、甘露梅は完成(おいしく食べられる)までに1年以上の年月を要する為つまらないので、それまでの間楽しめるものはないかとなったところ、梅酒なら飲める様になるまでに3ヶ月程度と期間も短く待つのも耐えられるかなとかそんな理由。
作り方は途中まで甘露梅とほとんど同じ。梅を洗ってへたを取ってビンに詰め込みます。量もそのまま1kg。その後同じように蜂蜜1kを流し込み準備完了。

違うのは最後の行程だけで、りんご酢の変わりに果実酒用のブランデー1800ccを注ぎます。梅酒の定番ホワイトリカーじゃないのは雰囲気出す為とホワイトリカーじゃつまらないため。
当然蜂蜜とブランデーの層ができるのできちんと混ざるまでは定期的にビンをまわしてかき混ぜることを忘れないようにお願いします。

糖分1kgは甘くなりすぎるとの懸念がありますが、個人的に甘くないお酒がおいしいと感じられない(ビール、焼酎など)のでおそらく大丈夫でしょう!多分。3ヵ月後に乞うご期待!?
ぽちっと応援お願いします↓ランキング見てニヤニヤさせてください<ニヤニヤ?
2008年06月30日
甘露梅作戦
以前のブログで触れたことがあるのが題名にもなっている甘露梅です。「かんろばい」って読みます。かんろうめでもなんでもいいと思いますが伝わればアリ。
で、初めて食べたその味にいたく感動した安い僕はそれを再び食べたくて食べたくて仕方なくなったご様子。ところがお店では簡単に発見することができなかったのでした。
だったら自作すればよくね?
というわけであっさりと自作承認が下りたのでやってみましょう作ってみましょう。
とここまであっさりと書いていますが、実際は梅の最高峰紀州南高梅の予約締め切りの関係ですでに3月には申し込んでいた為実に長い計画だったのでしたなんて壮大な!

ということで南高梅の到着です。

中身はこんな感じで詰まってます。

1個40g越えの驚愕の大きさですビッグベイト並み例えがおかしい。

前もってビンは洗っておいたので準備は万端です。
まずは梅をしっかり洗って水気を取ります。このとき水気をしっかりと取っていないと後々梅の痛みの元になりますので注意が必要です。乾燥のためにあまり放置しすぎても洗った意味が薄れるのでほどほどに。

洗ったら梅のへたというかなんというかまぁそんな感じのところをきちんと取り除くために楊枝でほじくります。梅の熟成度合いにもよりますが簡単に取れる場合とかなり苦労する場合があります。今回はいとも簡単に爪楊枝2本作戦でポロポロ取れてくれてラッキー。

こんな感じできれいすっきりになります。

ビンに詰めていきます。4Lのビンの推奨は梅1kgですのでそのくらいにしておきましょう。多すぎると失敗しますたぶん。

そしてここで蜂蜜を投入します。分量は1kgそれはもうたっぷりと注ぎ込みますプーさんも真っ青。

このくらいの位置まで入ります。この蜂蜜の量で甘さが決まってきますのでこのくらい入れときましょう。おそらく砂糖でも代用できますが蜂蜜は同量の砂糖に対してカロリーが低いのと風味がつくので断然お勧めです。

そしてこの後登場するのはりんご酢です。ここでは純りんご酢という純粋な酢を使います。飲用に加工されていないやつのことです。

どっぷどっぷと入れていきます。1Lですからこのサイズのりんご酢ですと丸々2本使うことになります。

トータルでこのくらいの位置まで水位は上昇ほぼ満水です完成。
梅の入手からここまでが長かったわけですが、ここからさらに甘露梅がおいしく食べられるまでなんと1年以上かかるとのこと気の長い話。
とはいえりんご酢がベースの梅ジュースが3ヶ月くらいで飲めるようになるとの話もありますので、完成までは細々と暮らしていきましょう。
ということで、これを都合4ビン作りました作りすぎ。
だって1ビンあたり30個ないわけですからこれでも1年間120個しか食べることができないわけですよ。振舞ったりなんだりを考えるとこれでも少ないかなと思うくらい。
ここまできて成功したか失敗したかの判定が1年以上先でないとわからないのも最高のギャンブル。すなわち成否のわからないまま来年のシーズンを迎えて漬け込みをすることになるわけですからもうその興奮ときたら!究極の変体。
はたして?
ぽちっと応援お願いします↓ランキング見てニヤニヤさせてください<ニヤニヤ?



で、初めて食べたその味にいたく感動した安い僕はそれを再び食べたくて食べたくて仕方なくなったご様子。ところがお店では簡単に発見することができなかったのでした。

だったら自作すればよくね?
というわけであっさりと自作承認が下りたのでやってみましょう作ってみましょう。

とここまであっさりと書いていますが、実際は梅の最高峰紀州南高梅の予約締め切りの関係ですでに3月には申し込んでいた為実に長い計画だったのでしたなんて壮大な!


ということで南高梅の到着です。

中身はこんな感じで詰まってます。

1個40g越えの驚愕の大きさですビッグベイト並み例えがおかしい。

前もってビンは洗っておいたので準備は万端です。
まずは梅をしっかり洗って水気を取ります。このとき水気をしっかりと取っていないと後々梅の痛みの元になりますので注意が必要です。乾燥のためにあまり放置しすぎても洗った意味が薄れるのでほどほどに。

洗ったら梅のへたというかなんというかまぁそんな感じのところをきちんと取り除くために楊枝でほじくります。梅の熟成度合いにもよりますが簡単に取れる場合とかなり苦労する場合があります。今回はいとも簡単に爪楊枝2本作戦でポロポロ取れてくれてラッキー。


こんな感じできれいすっきりになります。

ビンに詰めていきます。4Lのビンの推奨は梅1kgですのでそのくらいにしておきましょう。多すぎると失敗しますたぶん。

そしてここで蜂蜜を投入します。分量は1kgそれはもうたっぷりと注ぎ込みますプーさんも真っ青。

このくらいの位置まで入ります。この蜂蜜の量で甘さが決まってきますのでこのくらい入れときましょう。おそらく砂糖でも代用できますが蜂蜜は同量の砂糖に対してカロリーが低いのと風味がつくので断然お勧めです。


そしてこの後登場するのはりんご酢です。ここでは純りんご酢という純粋な酢を使います。飲用に加工されていないやつのことです。

どっぷどっぷと入れていきます。1Lですからこのサイズのりんご酢ですと丸々2本使うことになります。

トータルでこのくらいの位置まで水位は上昇ほぼ満水です完成。
梅の入手からここまでが長かったわけですが、ここからさらに甘露梅がおいしく食べられるまでなんと1年以上かかるとのこと気の長い話。

とはいえりんご酢がベースの梅ジュースが3ヶ月くらいで飲めるようになるとの話もありますので、完成までは細々と暮らしていきましょう。

ということで、これを都合4ビン作りました作りすぎ。

だって1ビンあたり30個ないわけですからこれでも1年間120個しか食べることができないわけですよ。振舞ったりなんだりを考えるとこれでも少ないかなと思うくらい。
ここまできて成功したか失敗したかの判定が1年以上先でないとわからないのも最高のギャンブル。すなわち成否のわからないまま来年のシーズンを迎えて漬け込みをすることになるわけですからもうその興奮ときたら!究極の変体。
はたして?
ぽちっと応援お願いします↓ランキング見てニヤニヤさせてください<ニヤニヤ?
2008年05月22日
続自作PEスティク
製造コスト的には大成功といってもいい自作PEスティック。 あとは実際の使い勝手ですからこの間作ったPEスティックでためしにFGノットしてみます。
あとは実際の使い勝手ですからこの間作ったPEスティックでためしにFGノットしてみます。

あー、なんというかすでにクイックノッター全く使ってませんせっかく買ったのに。 使っているリーダーが太いのもあるのでしょうが、クイックノッター使わなくても同じように編みこみすることができるのですビバ。
使っているリーダーが太いのもあるのでしょうが、クイックノッター使わなくても同じように編みこみすることができるのですビバ。

フワフワ感はクイックノッター使っても同じことですしだったら使わなくても一緒かなと。へたに力が入りすぎることもなく別段使用時と違いを感じることはできませんでした慣れってすごい。
・・・

・・・
感想はやりやすいの一言。今まで使っていた締め込みリングと違うところはまず巻きつけ数。締め込みリングの場合、10回くらいは巻きつけないとくるくる滑って使えなかったのが、こちらでは3~4回巻きつければ滑りません。
もう1つ便利な点はハーフヒッチを繰り返す際、リングでは先の理由でいちいちPEのあまり線を巻きなおすのが面倒すぎてやってられなかったのです。おまけに巻きつけ数が多いため余るPEの長さも結構なものになっていました。
それが数回巻きつけるだけですむのと、なによりその巻きつけるのがくるくるって感じですごい楽。リングは巻きつけるのに使用できる場所がほんのわずかでとても気を使ったのですが、PEスティックだと実際には5cmくらいの幅を利用できるので適当に巻きつけてもいけちゃうんです。
というわけでハーフヒッチ時の締め込みが今まで以上にしっかりできるので強度的にはさらなる向上が期待できます。

不安があるとすると、まだ力の入れ方や締めこむ角度などを体得していない為こんな感じでいびつな感じになってしまうこと。当然いびつなので引っ張ったときもPE側で切れてしまい逆に強度低下。 早急に練習を重ねる必要がありますね。
早急に練習を重ねる必要がありますね。
あとは無くさないように端っこに穴あけてリング通してスパイラルコードでもつないでおけば現場にも気軽に持って行けちゃうでしょう。オススメよ。
ぽちっと応援お願いします↓みなさんの応援で生かされてますよ?


 あとは実際の使い勝手ですからこの間作ったPEスティックでためしにFGノットしてみます。
あとは実際の使い勝手ですからこの間作ったPEスティックでためしにFGノットしてみます。

あー、なんというかすでにクイックノッター全く使ってませんせっかく買ったのに。
 使っているリーダーが太いのもあるのでしょうが、クイックノッター使わなくても同じように編みこみすることができるのですビバ。
使っているリーダーが太いのもあるのでしょうが、クイックノッター使わなくても同じように編みこみすることができるのですビバ。

フワフワ感はクイックノッター使っても同じことですしだったら使わなくても一緒かなと。へたに力が入りすぎることもなく別段使用時と違いを感じることはできませんでした慣れってすごい。
・・・

・・・
感想はやりやすいの一言。今まで使っていた締め込みリングと違うところはまず巻きつけ数。締め込みリングの場合、10回くらいは巻きつけないとくるくる滑って使えなかったのが、こちらでは3~4回巻きつければ滑りません。
もう1つ便利な点はハーフヒッチを繰り返す際、リングでは先の理由でいちいちPEのあまり線を巻きなおすのが面倒すぎてやってられなかったのです。おまけに巻きつけ数が多いため余るPEの長さも結構なものになっていました。

それが数回巻きつけるだけですむのと、なによりその巻きつけるのがくるくるって感じですごい楽。リングは巻きつけるのに使用できる場所がほんのわずかでとても気を使ったのですが、PEスティックだと実際には5cmくらいの幅を利用できるので適当に巻きつけてもいけちゃうんです。

というわけでハーフヒッチ時の締め込みが今まで以上にしっかりできるので強度的にはさらなる向上が期待できます。

不安があるとすると、まだ力の入れ方や締めこむ角度などを体得していない為こんな感じでいびつな感じになってしまうこと。当然いびつなので引っ張ったときもPE側で切れてしまい逆に強度低下。
 早急に練習を重ねる必要がありますね。
早急に練習を重ねる必要がありますね。あとは無くさないように端っこに穴あけてリング通してスパイラルコードでもつないでおけば現場にも気軽に持って行けちゃうでしょう。オススメよ。

ぽちっと応援お願いします↓みなさんの応援で生かされてますよ?
2008年05月20日
自作PEスティック
この間購入してきた自作の為の小物で実際に自作してみました。 買ってきたのは防振シート、塩ビパイプ、両面テープです。
買ってきたのは防振シート、塩ビパイプ、両面テープです。

まずは防振シートをカットして丁度いいサイズに切り取ります。ここでいう丁度いいサイズというのは塩ビパイプに巻きつけるための丁度いいサイズです。縦は塩ビパイプの長さが10cmなのでそのまま10cmでいいのですが、横の長さは実に微妙。
塩ビパイプには直径と内径が書いてあると思いますので直径×3.14で計算して下さい。ここでゆとり世代は注意が必要。なんといっても直径×おおよそ3ですからね。かなりの誤差が出ることになります的外れもいいところ。
僕は適当に計算して切り取って後はトライ&エラーで微調整です。具体的には切り取ったシートを巻きつけてみて、あまるようなら微妙に切り取っていきぴったりくるまでやり直しです。
こっちで試す場合は始めにある程度大きめにしておくことが重要です。小さくしちゃうとその時点で失敗作ですよ?
で、その後切り取った防振シートを塩ビパイプに両面テープで貼り付けます。

はい、ここにバカが1匹いますよー。両面てテープの厚みを計算に入れることなく塩ビパイプギリギリを攻めたおかげで長さが全然足りません。

このくらい足りないオーメン。

仕方ないのでもう1つ作ります。今度は瞬間接着剤を利用して貼り付けていきます。なぜならば最初の大きさに合わせてすでに防振シートを切り出してしまっているから先走り。
こっちは少しずつ少しずつ貼り付けていくのがポイント。一気にやるとうまくいかないばかりか乾くまで押さえておくのが大変なので、数センチずつ塗りこんで机に押さえこんで乾くのを待つとしっかり力も入ってうまくいくかも。

こちらは長さも丁度いい感じです。 端っこのぎざぎざ感が自作の印。
端っこのぎざぎざ感が自作の印。
耐久実験をしていいないので簡単に剥がれちゃうかもしれませんが、最大のメリットはその価格。今回両面テープは無駄な買い物になってしまいましたが、実際に使ったものだけでいけばPEスティック1組で300円かかってないという低価格ぶり。
売ってる奴は質感などに圧倒的な差はあるものの3K越えとその差約10倍。これは久々の成功じゃ?
ついに9万ヒット達成です!ありがとうみなさん、おめでとう俺。
次は10万ヒット目指していきますよー。懲りずにおつきあいくださいませ。
ぽちっと応援お願いします↓みなさんの応援で生かされてますよ?


 買ってきたのは防振シート、塩ビパイプ、両面テープです。
買ってきたのは防振シート、塩ビパイプ、両面テープです。
まずは防振シートをカットして丁度いいサイズに切り取ります。ここでいう丁度いいサイズというのは塩ビパイプに巻きつけるための丁度いいサイズです。縦は塩ビパイプの長さが10cmなのでそのまま10cmでいいのですが、横の長さは実に微妙。

塩ビパイプには直径と内径が書いてあると思いますので直径×3.14で計算して下さい。ここでゆとり世代は注意が必要。なんといっても直径×おおよそ3ですからね。かなりの誤差が出ることになります的外れもいいところ。

僕は適当に計算して切り取って後はトライ&エラーで微調整です。具体的には切り取ったシートを巻きつけてみて、あまるようなら微妙に切り取っていきぴったりくるまでやり直しです。
こっちで試す場合は始めにある程度大きめにしておくことが重要です。小さくしちゃうとその時点で失敗作ですよ?
で、その後切り取った防振シートを塩ビパイプに両面テープで貼り付けます。

はい、ここにバカが1匹いますよー。両面てテープの厚みを計算に入れることなく塩ビパイプギリギリを攻めたおかげで長さが全然足りません。


このくらい足りないオーメン。


仕方ないのでもう1つ作ります。今度は瞬間接着剤を利用して貼り付けていきます。なぜならば最初の大きさに合わせてすでに防振シートを切り出してしまっているから先走り。
こっちは少しずつ少しずつ貼り付けていくのがポイント。一気にやるとうまくいかないばかりか乾くまで押さえておくのが大変なので、数センチずつ塗りこんで机に押さえこんで乾くのを待つとしっかり力も入ってうまくいくかも。

こちらは長さも丁度いい感じです。
 端っこのぎざぎざ感が自作の印。
端っこのぎざぎざ感が自作の印。耐久実験をしていいないので簡単に剥がれちゃうかもしれませんが、最大のメリットはその価格。今回両面テープは無駄な買い物になってしまいましたが、実際に使ったものだけでいけばPEスティック1組で300円かかってないという低価格ぶり。

売ってる奴は質感などに圧倒的な差はあるものの3K越えとその差約10倍。これは久々の成功じゃ?
ついに9万ヒット達成です!ありがとうみなさん、おめでとう俺。
次は10万ヒット目指していきますよー。懲りずにおつきあいくださいませ。
ぽちっと応援お願いします↓みなさんの応援で生かされてますよ?
2008年05月03日
エギ王Qをロケッティア化で飛距離アップ
日の出の時間を考えて今日は5時に起きました。 ホントは4時15分に目覚ましをセットしていたのですが、いざ目を覚ましてみればあまりにも真っ暗でいくらなんでもこれでは・・・と思い二度寝してしまった次第ですまる。
ホントは4時15分に目覚ましをセットしていたのですが、いざ目を覚ましてみればあまりにも真っ暗でいくらなんでもこれでは・・・と思い二度寝してしまった次第ですまる。
やはり明るいところでなにをしているか見える中釣りをするほうが、真っ暗な中で釣りをするよりも面白いですからね。 釣れる釣れないは別にして。
釣れる釣れないは別にして。

ということで準備をして釣り場に下りると5時30分。今日はどうにも風向きが悪く東からの風が強いので今のところ知っているどこに行ってもアウトな予感。
キャストしてもとにかく飛ばないのでいったいぜんたいどうしたものか・・・。 こうなったらアレを試すときがきたようです。構想だけは暖め続け密かに準備はしていたものの、いかんせん踏ん切りがつかずに今まで来てしまったアレを!
こうなったらアレを試すときがきたようです。構想だけは暖め続け密かに準備はしていたものの、いかんせん踏ん切りがつかずに今まで来てしまったアレを!
で、アレってなに?

コレですコレ!
よく分からないって?写真でいけば左のほう、カンナのちと左をご覧頂きたい。オレンジの玉が見えるでしょうか?そうこれは先日イカ用の小物入れの中に彩として入っていたしもり浮きです。
はい、この写真をみてすでにお気づきの方も多いはず。超勘のいいかたはすでにケースの中にしもり浮きを見つけた時点でばれていたはずですよさすがするどい!
何のことか分からない人のために説明しますと、某メーカーのエギにロケッティアというぶっとびのエギがありまして、その革命的なシステムをそれ以外のエギでパクってやれという通称「ロケッティア化」です。
まだ足りない?ではロケッティアの仕組みを説明します。
通常エギをキャストすると、当然カンナ側を進行方向に向けて飛んでいくわけです。エギの頭にラインが結んであって振り子にして投げるのでそれは当然。
しかし、それだとオモリが後方にあるため飛行姿勢も安定しないばかりか飛距離ものびません。 このあたりは飛距離を売り物にして重心移動システムを採用しているルアーを見ても明らかです。飛ぶときは飛行方向にウェイトがあり、着水後リトリーブ開始でアイ方向に移動してくる例のアレですね。
このあたりは飛距離を売り物にして重心移動システムを採用しているルアーを見ても明らかです。飛ぶときは飛行方向にウェイトがあり、着水後リトリーブ開始でアイ方向に移動してくる例のアレですね。
ということは、エギもウェイトを先に飛んでいけば飛距離が伸びることになりますが、重心移動を採用しているのはダイワのエギくらいでしょうか。それでもシンカーのそもそもの位置や重さを移動しているわけではないので本物とはいえません。
で、ロケッティアはそのあたりを工夫してシンカーから飛んでいくシステムを搭載して発売してるわけです。 当然シンカーの形状などにも秘密があるようですがそんなものまでは真似しようがないので、システムのみ
当然シンカーの形状などにも秘密があるようですがそんなものまでは真似しようがないので、システムのみパクるリスペクトすることにします。

まず、エギを結ぶ前にラインにしもり浮きを通しておきます。そのご普通にスナップを介してエギを接続します。浮きはラインを通して自由に動く状態ですね。

で、次にエギの外側のカンナの背中側中央部分の1本をこのように延ばします。ペンチなどを使ってできるだけまっすぐ伸ばしてください。指力に自信のある人はものをいわせるのもありです怪我に気をつけて。実際には丁度中央にあるケースは稀で、ひどいとかなり中心からずれているケースもありますが、できるだけ中心にしてください曲げ方で工夫。

しかる後にスナップ側からラインをエギの背中に沿って回しますこんな感じ。突然エギのカラーが変わってますが気にしない。ラインがピンクだったので見づらくてチェンジしました。

最終的に一番最初に通しておいたしもり浮きでラインが簡単に動かないように固定します。これで普段とは逆向きにエギがぶら下がることになりますビバ逆立ち。
で、あとはこの状態でぶん投げればシンカー側からめでたく飛んでいきそれはそれはすばらしい飛距離が得られるとそういう具合です。
見事着水後はしもり浮きの浮力でストッパーがはずれ、いつもと同じようにエギは沈んでいくのでそのまんまってこともありませんすげえなんて画期的なシステム。
特許らしいのですが個人でパクって使う分には問題ありますまい。でもリスペクトは忘れない。
ここで個人の工夫ポイントは3つ。
まず1つ目はしもり浮きの穴の大きさ。つるしの状態ではラインを通すことはたやすくてもカンナを通すのは難しいサイズ(僕の買ってきた奴の場合)のはずです。
適当に千枚通しなどで拡張しておきましょう適当にですよ拡張しすぎも逆効果。このあたりは実際にラインに通したしもり浮きをカンナに通してみてスムーズに動く大きさを見極めてください。
さらに穴にはテーパーが付いているので、カンナ側に大きい方を持ってくるようにしてください。スムーズに浮きが外れないと本末転倒で飛んだはいいけれどイカが釣れませんたぶん。

2つ目は伸ばしたカンナの角度です。これは完全にロケッティアの箱の裏書からパクってますが実体験も含めて確かにそのとうり。このカンナの角度を倒しすぎた場合、しもり浮きがキャスト中に外れてしまってうまくシンカーを先に飛んでいきません。それどころか飛行姿勢が著しく乱れて逆に飛ばなくなります。
逆に立てすぎてエギと一直線に近くした場合、投げるときはびしっと安定してシンカーから飛んでいって気持ちいいのですが、着水後しもり浮きがカンナから外れにくくなってしまい当然穴の大きさが適当でないときと同じ結果になります。
3つ目は内側のカンナの角度。最初にカンナを伸ばしたときにちょうど中央の針が伸ばせることは稀だと書きましたが、カンナの取り付けががっちり決まっているわけではないのでそのようなことになるのですが、当然内側も連動してますからずれてます。
で、背中を這わせたラインが針と針の間を通っていくわけですが、カンナの角度によってはラインが絡んでしまいこれまたスムーズにラインがカンナから外れません。

そうならないように中央付近のカンナを若干外向きに曲げます。あんまり無茶しすぎるとフッキングに影響が出る恐れもありますから適度に曲げましょう。何事も中庸が一番です。 写真見づらくてごめんさない。写真でいくと下側のカンナの真ん中へんをハの字型に開いとくということです。
写真見づらくてごめんさない。写真でいくと下側のカンナの真ん中へんをハの字型に開いとくということです。
こうすることによって浮きが外れる前後にラインがカンナに絡みにくいんじゃないかなと思ってます。実際はどうだか不明ですが言われて見ればそんな気がしませんか?気分の問題なの?
このあたりを掴むまで結構苦戦します。失敗例はそれぞれ書いたとおりです。中でも2つ目の角度の問題が一番シリアスかも知れません。キャスト中に浮きが外れずに飛ばせるのと、着水後に浮きが外れてくれることの両立が実に難しい試行錯誤です。
このあたりロケッティアはうまく作ってあるのかも知れませんが実物持ってないので不明です。真の勇者は1個買って研究してください。僕はパッケージの裏書立ち読みですませました偽勇者なのであくまでリスペクトのみ精神世界。
うわ、めっちゃ長くなってしまったので串本釣行の本編は次回です明日に続くぅ!
ぽちっと応援お願いします↓みなさんの応援で生かされてますよ?


 ホントは4時15分に目覚ましをセットしていたのですが、いざ目を覚ましてみればあまりにも真っ暗でいくらなんでもこれでは・・・と思い二度寝してしまった次第ですまる。
ホントは4時15分に目覚ましをセットしていたのですが、いざ目を覚ましてみればあまりにも真っ暗でいくらなんでもこれでは・・・と思い二度寝してしまった次第ですまる。
やはり明るいところでなにをしているか見える中釣りをするほうが、真っ暗な中で釣りをするよりも面白いですからね。
 釣れる釣れないは別にして。
釣れる釣れないは別にして。

ということで準備をして釣り場に下りると5時30分。今日はどうにも風向きが悪く東からの風が強いので今のところ知っているどこに行ってもアウトな予感。

キャストしてもとにかく飛ばないのでいったいぜんたいどうしたものか・・・。
 こうなったらアレを試すときがきたようです。構想だけは暖め続け密かに準備はしていたものの、いかんせん踏ん切りがつかずに今まで来てしまったアレを!
こうなったらアレを試すときがきたようです。構想だけは暖め続け密かに準備はしていたものの、いかんせん踏ん切りがつかずに今まで来てしまったアレを!で、アレってなに?

コレですコレ!

よく分からないって?写真でいけば左のほう、カンナのちと左をご覧頂きたい。オレンジの玉が見えるでしょうか?そうこれは先日イカ用の小物入れの中に彩として入っていたしもり浮きです。
はい、この写真をみてすでにお気づきの方も多いはず。超勘のいいかたはすでにケースの中にしもり浮きを見つけた時点でばれていたはずですよさすがするどい!

何のことか分からない人のために説明しますと、某メーカーのエギにロケッティアというぶっとびのエギがありまして、その革命的なシステムをそれ以外のエギでパクってやれという通称「ロケッティア化」です。
まだ足りない?ではロケッティアの仕組みを説明します。
通常エギをキャストすると、当然カンナ側を進行方向に向けて飛んでいくわけです。エギの頭にラインが結んであって振り子にして投げるのでそれは当然。
しかし、それだとオモリが後方にあるため飛行姿勢も安定しないばかりか飛距離ものびません。
 このあたりは飛距離を売り物にして重心移動システムを採用しているルアーを見ても明らかです。飛ぶときは飛行方向にウェイトがあり、着水後リトリーブ開始でアイ方向に移動してくる例のアレですね。
このあたりは飛距離を売り物にして重心移動システムを採用しているルアーを見ても明らかです。飛ぶときは飛行方向にウェイトがあり、着水後リトリーブ開始でアイ方向に移動してくる例のアレですね。ということは、エギもウェイトを先に飛んでいけば飛距離が伸びることになりますが、重心移動を採用しているのはダイワのエギくらいでしょうか。それでもシンカーのそもそもの位置や重さを移動しているわけではないので本物とはいえません。
で、ロケッティアはそのあたりを工夫してシンカーから飛んでいくシステムを搭載して発売してるわけです。
 当然シンカーの形状などにも秘密があるようですがそんなものまでは真似しようがないので、システムのみ
当然シンカーの形状などにも秘密があるようですがそんなものまでは真似しようがないので、システムのみ
まず、エギを結ぶ前にラインにしもり浮きを通しておきます。そのご普通にスナップを介してエギを接続します。浮きはラインを通して自由に動く状態ですね。

で、次にエギの外側のカンナの背中側中央部分の1本をこのように延ばします。ペンチなどを使ってできるだけまっすぐ伸ばしてください。指力に自信のある人はものをいわせるのもありです怪我に気をつけて。実際には丁度中央にあるケースは稀で、ひどいとかなり中心からずれているケースもありますが、できるだけ中心にしてください曲げ方で工夫。


しかる後にスナップ側からラインをエギの背中に沿って回しますこんな感じ。突然エギのカラーが変わってますが気にしない。ラインがピンクだったので見づらくてチェンジしました。

最終的に一番最初に通しておいたしもり浮きでラインが簡単に動かないように固定します。これで普段とは逆向きにエギがぶら下がることになりますビバ逆立ち。

で、あとはこの状態でぶん投げればシンカー側からめでたく飛んでいきそれはそれはすばらしい飛距離が得られるとそういう具合です。
見事着水後はしもり浮きの浮力でストッパーがはずれ、いつもと同じようにエギは沈んでいくのでそのまんまってこともありませんすげえなんて画期的なシステム。

特許らしいのですが個人でパクって使う分には問題ありますまい。でもリスペクトは忘れない。
ここで個人の工夫ポイントは3つ。
まず1つ目はしもり浮きの穴の大きさ。つるしの状態ではラインを通すことはたやすくてもカンナを通すのは難しいサイズ(僕の買ってきた奴の場合)のはずです。
適当に千枚通しなどで拡張しておきましょう適当にですよ拡張しすぎも逆効果。このあたりは実際にラインに通したしもり浮きをカンナに通してみてスムーズに動く大きさを見極めてください。
さらに穴にはテーパーが付いているので、カンナ側に大きい方を持ってくるようにしてください。スムーズに浮きが外れないと本末転倒で飛んだはいいけれどイカが釣れませんたぶん。

2つ目は伸ばしたカンナの角度です。これは完全にロケッティアの箱の裏書からパクってますが実体験も含めて確かにそのとうり。このカンナの角度を倒しすぎた場合、しもり浮きがキャスト中に外れてしまってうまくシンカーを先に飛んでいきません。それどころか飛行姿勢が著しく乱れて逆に飛ばなくなります。

逆に立てすぎてエギと一直線に近くした場合、投げるときはびしっと安定してシンカーから飛んでいって気持ちいいのですが、着水後しもり浮きがカンナから外れにくくなってしまい当然穴の大きさが適当でないときと同じ結果になります。

3つ目は内側のカンナの角度。最初にカンナを伸ばしたときにちょうど中央の針が伸ばせることは稀だと書きましたが、カンナの取り付けががっちり決まっているわけではないのでそのようなことになるのですが、当然内側も連動してますからずれてます。
で、背中を這わせたラインが針と針の間を通っていくわけですが、カンナの角度によってはラインが絡んでしまいこれまたスムーズにラインがカンナから外れません。

そうならないように中央付近のカンナを若干外向きに曲げます。あんまり無茶しすぎるとフッキングに影響が出る恐れもありますから適度に曲げましょう。何事も中庸が一番です。
 写真見づらくてごめんさない。写真でいくと下側のカンナの真ん中へんをハの字型に開いとくということです。
写真見づらくてごめんさない。写真でいくと下側のカンナの真ん中へんをハの字型に開いとくということです。こうすることによって浮きが外れる前後にラインがカンナに絡みにくいんじゃないかなと思ってます。実際はどうだか不明ですが言われて見ればそんな気がしませんか?気分の問題なの?
このあたりを掴むまで結構苦戦します。失敗例はそれぞれ書いたとおりです。中でも2つ目の角度の問題が一番シリアスかも知れません。キャスト中に浮きが外れずに飛ばせるのと、着水後に浮きが外れてくれることの両立が実に難しい試行錯誤です。

このあたりロケッティアはうまく作ってあるのかも知れませんが実物持ってないので不明です。真の勇者は1個買って研究してください。僕はパッケージの裏書立ち読みですませました偽勇者なのであくまでリスペクトのみ精神世界。
うわ、めっちゃ長くなってしまったので串本釣行の本編は次回です明日に続くぅ!
ぽちっと応援お願いします↓みなさんの応援で生かされてますよ?
2007年06月18日
ラバージグ用ソークオイル
ラバージグを自作する際その作りかたをネットで調べたわけですが、その中で多かったのが作成後のソークを薦める内容。ソーク?はてソーク?何のことかはよく分かりませんが、どうやらオイルをラバーに浸透させる行為のことをそう呼ぶようです。
とりあえず使用前と使用後の違いを明確にする為にしばらくはソークしないで作成してきたのですが、根はオタク気質なものですからこりたくなるわけです。そうなるともうソークしたくていてもたってもいられないわけでどんな中毒?

で「エコギア パワーオイル ラバー用」を買ってきました。ついでに小物もワーム用オイルも同じ大きさの容器で販売されているので間違えないように要注意だ。ボトルの色が違うので普通は間違えない。はたしてソークによってどのような効果があらわれるのでしょうか?
その説明書きを読むと・・・
●ラバージグをビニール袋などに入れ、15分程度ソークしてください。
●白い粉が消え、ラバースカートの太さと長さが増します。
●ラバースカートの1本1本がソフトになり、水中でのアクションにリアル感が出ます。
●”味と匂い”が染みこんで集魚力がアップします。
これはすごいですよ?太さと長さが増すわけです恐ろしい。
さっそく使用方法を読んでやってみましょう。

ビニール袋にソークしたいラバージグを投入し、オイルも適量投入します。ソークしてくださいの意味が分からないのでとりあえずラバーになじませておきますなじませるの意味だと勝手に解釈です。と思ってちょいとネットで調べてみたところ「浸す、浸透させる」という意味らしいですぞ?近からず遠からず。

で、説明書きどうり15分程度放置した物がこちら。このあとオイルを洗い流して乾燥させれば完成です。どうでしょう、ソーク前とソーク後の違いがお分かりいただけるでしょうか?


並べてみました。ふむ、確かに違いがわかるようなわからないような。ラバーの太さが一回り太くなって心なしか色もはっきりしています。すでに一度カットしているにもかかわらず再度トリミングしていますからラバーの長さも伸びているようです。
しかし、ついでにオイルの「匂い」が染み付いてとんでもないことになってくれています。一般的に臭いといわれるものではないと思いますがなんともいえない匂いを発生させていますオイルの匂いが染み付いた感じ。これで釣果に差が生まれるかと思うとドキドキワクワクですが部屋に漂うのは勘弁してもらいたいですピンチ。

おまけで水中の画像。洗面台でのものですが気持ちフレア感が出ているような気もします。
おまけ2。ナチュラムさんから間違えて右側を頼んでしまったフローターのバッグが届きました。 これで左右そろいましたがめちゃんこ迷惑をかけてしまいました。しかしそれになにも言わずに対応してくれたのでものすごい感謝感激です。これからもついていきますよー。
これで左右そろいましたがめちゃんこ迷惑をかけてしまいました。しかしそれになにも言わずに対応してくれたのでものすごい感謝感激です。これからもついていきますよー。

とりあえず使用前と使用後の違いを明確にする為にしばらくはソークしないで作成してきたのですが、根はオタク気質なものですからこりたくなるわけです。そうなるともうソークしたくていてもたってもいられないわけでどんな中毒?


で「エコギア パワーオイル ラバー用」を買ってきました。ついでに小物もワーム用オイルも同じ大きさの容器で販売されているので間違えないように要注意だ。ボトルの色が違うので普通は間違えない。はたしてソークによってどのような効果があらわれるのでしょうか?
その説明書きを読むと・・・
●ラバージグをビニール袋などに入れ、15分程度ソークしてください。
●白い粉が消え、ラバースカートの太さと長さが増します。
●ラバースカートの1本1本がソフトになり、水中でのアクションにリアル感が出ます。
●”味と匂い”が染みこんで集魚力がアップします。
これはすごいですよ?太さと長さが増すわけです恐ろしい。

さっそく使用方法を読んでやってみましょう。

ビニール袋にソークしたいラバージグを投入し、オイルも適量投入します。ソークしてくださいの意味が分からないのでとりあえずラバーになじませておきますなじませるの意味だと勝手に解釈です。と思ってちょいとネットで調べてみたところ「浸す、浸透させる」という意味らしいですぞ?近からず遠からず。

で、説明書きどうり15分程度放置した物がこちら。このあとオイルを洗い流して乾燥させれば完成です。どうでしょう、ソーク前とソーク後の違いがお分かりいただけるでしょうか?


並べてみました。ふむ、確かに違いがわかるようなわからないような。ラバーの太さが一回り太くなって心なしか色もはっきりしています。すでに一度カットしているにもかかわらず再度トリミングしていますからラバーの長さも伸びているようです。
しかし、ついでにオイルの「匂い」が染み付いてとんでもないことになってくれています。一般的に臭いといわれるものではないと思いますがなんともいえない匂いを発生させていますオイルの匂いが染み付いた感じ。これで釣果に差が生まれるかと思うとドキドキワクワクですが部屋に漂うのは勘弁してもらいたいですピンチ。


おまけで水中の画像。洗面台でのものですが気持ちフレア感が出ているような気もします。
おまけ2。ナチュラムさんから間違えて右側を頼んでしまったフローターのバッグが届きました。
 これで左右そろいましたがめちゃんこ迷惑をかけてしまいました。しかしそれになにも言わずに対応してくれたのでものすごい感謝感激です。これからもついていきますよー。
これで左右そろいましたがめちゃんこ迷惑をかけてしまいました。しかしそれになにも言わずに対応してくれたのでものすごい感謝感激です。これからもついていきますよー。
2007年06月16日
新色ラバー導入
自作に華がさくラバジ道ですが、ノーマルラバジは黒系、スモラバは派手系とはっきり分かれる作り方をしてきたのですがやはりラバジも派手系のものを作りたくなるのが人情というものそのような人情はない。

で、購入してきたカラーは白とチャートこれまたある意味無難な色を選択しましたね安定最高! あとはジグヘッドがないと作れませんから以前から気になっていた1/2のタングステン製アーキーヘッドのZAPPPUエコヘッドと大きさの小さい奴を買ってきました。ガマカツのコブラヘッドや、ラッキークラフトのグラファイトジグと形を比較してみます。左からコブラ、グラファイト、ZAPPU。
あとはジグヘッドがないと作れませんから以前から気になっていた1/2のタングステン製アーキーヘッドのZAPPPUエコヘッドと大きさの小さい奴を買ってきました。ガマカツのコブラヘッドや、ラッキークラフトのグラファイトジグと形を比較してみます。左からコブラ、グラファイト、ZAPPU。

あきらかにコブラヘッドとは一線を画す形をしています。グラファイトジグもコブラに近い丸型といったところなのでZAPPU製のこのエコヘッドはかなり極端な丸型ティアドロップ型とでもいいましょうかそんな形。
プラグやスモラバはチャート系がありでラバジだけなしなわけはないはずですから、多分みんな使っているか使ってないかの違いではないかと予想。ここはもっと派手系ラバジを普及させる意味でも積極的に作っていきたい!


さっそく1個作ってみましたこんな感じ。どう?やっぱり見慣れていないだけに釣れる気がしない・・・。だってそもそもラバジでもスモラバでも僕はまだ釣ったことがないんだもの。


で、購入してきたカラーは白とチャートこれまたある意味無難な色を選択しましたね安定最高!
 あとはジグヘッドがないと作れませんから以前から気になっていた1/2のタングステン製アーキーヘッドのZAPPPUエコヘッドと大きさの小さい奴を買ってきました。ガマカツのコブラヘッドや、ラッキークラフトのグラファイトジグと形を比較してみます。左からコブラ、グラファイト、ZAPPU。
あとはジグヘッドがないと作れませんから以前から気になっていた1/2のタングステン製アーキーヘッドのZAPPPUエコヘッドと大きさの小さい奴を買ってきました。ガマカツのコブラヘッドや、ラッキークラフトのグラファイトジグと形を比較してみます。左からコブラ、グラファイト、ZAPPU。
あきらかにコブラヘッドとは一線を画す形をしています。グラファイトジグもコブラに近い丸型といったところなのでZAPPU製のこのエコヘッドはかなり極端な丸型ティアドロップ型とでもいいましょうかそんな形。
プラグやスモラバはチャート系がありでラバジだけなしなわけはないはずですから、多分みんな使っているか使ってないかの違いではないかと予想。ここはもっと派手系ラバジを普及させる意味でも積極的に作っていきたい!


さっそく1個作ってみましたこんな感じ。どう?やっぱり見慣れていないだけに釣れる気がしない・・・。だってそもそもラバジでもスモラバでも僕はまだ釣ったことがないんだもの。
2007年06月12日
ワレット改良
昨日紹介したワレットにさっそくスプーンを移し変えて収めてみるのですがここで問題がひとつ発生。ドリームマスターは真ん中にビニールの仕切りがあったのでスプーン同士が直接背中合わせになって接触することがなかったのですが、今回のワレットにはそれがない。ないから接触して傷がつく。釣りに使っての傷なら我慢できるが関係ないところで付く傷なんて許せるわけがない。
さらに塗装がはげたりしたらせっかくのカラーが台無しですからそれは防がなくてはいけないでしょう。
ということでなんとかドリームマスターシステムを再現できないかとホームセンターでちょいと部品調達。

買ってきたのは一番薄い防振シートと強力テープ。防振シートは適当なのがなかったので選んできただけですから薄くてゴムっぽいある程度スプーンを固定しておけるような素材でしたらなんでもいいのではないでしょうか。

まず防振シートをワレットの仕切りの形にあわせて切り出します。

次に強力テープを使って仕切りと仕切りの間に防振シートをなんとか固定しますこのあたりが適当なんとかって。

ホイ、完成こんな感じ。これでスプーンの背中同士が直接接触することもありますまい。割とワレットの厚みは増したもののそんなことは些細なこと。かなりチャックを閉めるのに強引な感じがするがそんなことは些細なこと。このままではそのうち開閉時にチャックが壊れそうな雰囲気すらあるがそんなことは些細なことなわけがない!
まぁ、そんな時のために予備を買ったんですよ予備をそうなの?

さらに塗装がはげたりしたらせっかくのカラーが台無しですからそれは防がなくてはいけないでしょう。
ということでなんとかドリームマスターシステムを再現できないかとホームセンターでちょいと部品調達。

買ってきたのは一番薄い防振シートと強力テープ。防振シートは適当なのがなかったので選んできただけですから薄くてゴムっぽいある程度スプーンを固定しておけるような素材でしたらなんでもいいのではないでしょうか。

まず防振シートをワレットの仕切りの形にあわせて切り出します。

次に強力テープを使って仕切りと仕切りの間に防振シートをなんとか固定しますこのあたりが適当なんとかって。

ホイ、完成こんな感じ。これでスプーンの背中同士が直接接触することもありますまい。割とワレットの厚みは増したもののそんなことは些細なこと。かなりチャックを閉めるのに強引な感じがするがそんなことは些細なこと。このままではそのうち開閉時にチャックが壊れそうな雰囲気すらあるがそんなことは些細なことなわけがない!

まぁ、そんな時のために予備を買ったんですよ予備をそうなの?
2007年06月09日
スモラバ自作
今回はスモールラバージグ略してスモラバの自作方法の紹介です。基本的には前回のラバジとそんな違いはありませんから大丈夫安心してください簡単だよ?たぶん。

まずはラバージグと同じようにジグヘッドをバイスに固定します。僕が買ってきたのはZAPPUのラウンドヘッドインチの1/32オンスです。フックサイズは4号。見た目で売ってるスモラバと同じくらいの大きさのを選びました見た目かよ。
これまた同じようにスレッドで下巻きをします。これで巻いたラバーの滑り止めにします。ゴムなのに滑り止めが必要なのが不思議な感じ。

次に使うラバーをチョイスして適宜カットします。使う量はラバジよりも少し少なく2枚。市販されているスモラバを見るとそれほどラバーの量は多くないのでこれくらいでいいんではないかとそんな理由。この辺は好みの問題とオリジナリティーですからお好きなだけどうぞ。使っているのはガマカツのシリコンスカートです。0.6mmのほう。

スモラバ用に買ったラバーは幅が短いので特に半分に裂いたりはしません大した違いはでないでしょうこのあたり自作感たっぷり。そいつをジグヘッドの上下に巻きます。とりあえずここは片方ずつやりましょう。両方いっぺんにやるのは手が2本しかない僕にはちとしんどい。

で、共にスレッドで数回巻いて結んでとめます。最後にスレッドをハーフヒッチってやつで何回か止めて念のため瞬間接着剤を塗布して終了です。この辺はラバジとほとんど同じですね。そのあとラバーの端っこを引っ張って切っていくのも同じ作業です。

こんな感じで出来上がりますので、ここからもラバジ同様長いラバーをカットして整えます。このカットのセンスもオリジナリティが発揮されると思いますのでセンスの全てをぶつけてください。うまくフレアするとかっこいいですね。僕はうまくいきませんが。
それで完成。ジグヘッドがタングステン樹脂のものでも高額ではないため1個200円以下でできると思います。
総投資・・・9094円、総製作・・・7個、単価・・・1300円。まだめちゃ高額。

まずはラバージグと同じようにジグヘッドをバイスに固定します。僕が買ってきたのはZAPPUのラウンドヘッドインチの1/32オンスです。フックサイズは4号。見た目で売ってるスモラバと同じくらいの大きさのを選びました見た目かよ。

これまた同じようにスレッドで下巻きをします。これで巻いたラバーの滑り止めにします。ゴムなのに滑り止めが必要なのが不思議な感じ。


次に使うラバーをチョイスして適宜カットします。使う量はラバジよりも少し少なく2枚。市販されているスモラバを見るとそれほどラバーの量は多くないのでこれくらいでいいんではないかとそんな理由。この辺は好みの問題とオリジナリティーですからお好きなだけどうぞ。使っているのはガマカツのシリコンスカートです。0.6mmのほう。

スモラバ用に買ったラバーは幅が短いので特に半分に裂いたりはしません大した違いはでないでしょうこのあたり自作感たっぷり。そいつをジグヘッドの上下に巻きます。とりあえずここは片方ずつやりましょう。両方いっぺんにやるのは手が2本しかない僕にはちとしんどい。


で、共にスレッドで数回巻いて結んでとめます。最後にスレッドをハーフヒッチってやつで何回か止めて念のため瞬間接着剤を塗布して終了です。この辺はラバジとほとんど同じですね。そのあとラバーの端っこを引っ張って切っていくのも同じ作業です。

こんな感じで出来上がりますので、ここからもラバジ同様長いラバーをカットして整えます。このカットのセンスもオリジナリティが発揮されると思いますのでセンスの全てをぶつけてください。うまくフレアするとかっこいいですね。僕はうまくいきませんが。
それで完成。ジグヘッドがタングステン樹脂のものでも高額ではないため1個200円以下でできると思います。
総投資・・・9094円、総製作・・・7個、単価・・・1300円。まだめちゃ高額。
2007年06月08日
ラバージグ自作
みなさんお待たせしました待ってない?いやいやいやいやそこは嘘でも待っていたと言ってくれないと。ラバージグ自作のコーナーです。
スモラバとラバジどちらから先に作成するか悩みましたが、なんとなく多少失敗してもごまかしがききそうなのでラバジから作ることに決めました弱腰な僕。出る前から負ける事考える馬鹿いるかよ!(by猪木)

まずは準備から。バイスを机に固定します。ちなみにバイスってのは万力のことですから専用の物じゃなくても大丈夫ですが専用を使ったほうが気分出るので安いのでいいから買いましょう。2000円弱です。

さらにボビンホルダーにボビンをくっつけて糸を出しておきます。はさむのは見たまんま普通にはさんでもらってスレッド(糸)は先端の筒から出しておきます。糸を簡単に出す為にスレッダーとかいう道具も出てるようですが買って使うほど難しい作業でもないので必要なし。不器用度に自信のある人は買っておきましょう。

バイスにジグヘッドをはさみます。今回はコブラヘッドを使います。僕はフックを下向きに挟んでみましたが向きはどっちでもいいんじゃないでしょうか?お好みでどうぞ。下手な挟み方をすると作業中にジグヘッドが飛んで来ることになるのでしっかりはさんで動かないか確認しておきましょう。
その後にスレッドで下巻きをしておきます。これをやっておくと後半でラバーを巻いたときにずれにくいはずです。面倒なら飛ばしてしまってもいいでしょう。このへんは自作の良さ売り物じゃないから気分次第で適当に行きましょう。

使いたいカラーのラバーを10cmくらいに切って2~4枚用意してそれを半分に裂いておきます。縦の切れ目が入っていますから手で簡単に裂けます。僕は黒2枚、茶1枚を半分に裂いたので6枚あります。完成後のボリュームが変わってきますのでこのあたりの量もお好みでどうぞ。

続いてラバーをジグヘッドに巻いていきます。ジグヘッドの先ほど下巻きをしたところにラバーの中央がくるように乗っけてスレッドで巻いていきます。このあたりきつめに巻いていかないと出来上がりがぶちゃいくになるばかりかラバーがずれてとんでもないことになるのでしっかり締めこんでいきましょう。1枚乗っけるたびに1~2周きっちり締めこめば十分でしょう。あんまり巻きすぎてもかさばってうまく仕上がりませんから注意。
乗っけていくラバーの色の順番で仕上がり時の見え方が違うのでこのあたりにセンスが出るといえます。

で、全てのラバーを巻き終わったらしっかりとスレッドで締めこんだ後接着剤でスレッドがほどけないようにとめてしまいます。接着剤の量に最新の注意を払わないとうまく広がりませんので慎重に。そしたらラバーを全部フック側に追いやります。普通に追いやればいい感じになると思いますが言うことを聞かない場合は追いやった後にスレッドで一巻きしてとめちゃいましょう。自作ですからそれもアリです。
作業も残すところ後少し頑張っていきましょう。

ラバーを1片ずつつまんで引っ張ります。そしてはさみを使って端からゆっくりと切っていきます。しっかり引っ張っていれば面白いようにパラパラばらけていきます。それを全てのラバー片に行っていきます。僕は6枚使ったので6回やるわけですね。
全て切り終わったらざっと確認して全てのラバーがばらけているかを確認してください。中にはガッツでくっついたままの部分があります気合が入ったラバーです。そのままというのも味がありますが最初くらいはしっかり全部のラバーにばらけてもらいましょう。

完成です。この後全体のラバーの長さを好みの長さになるまで刈り込んで仕上げです。

はい、僕の自作ラバージグ第一号ですが余裕の失敗です。根元にラバーを巻かなくてはいけないのに楽勝で1段先のワームキーパーに巻いています(笑)途中で気がつきましたが後戻りはできません過酷な旅路。 このあとフックガードのブラシを必要な人はくっつけます。ゼリー状の瞬間接着剤で穴に固定してください。
このあとフックガードのブラシを必要な人はくっつけます。ゼリー状の瞬間接着剤で穴に固定してください。
この接着剤は必ずゼリー状のものにすること。これは絶対です。とはいえ、自作なんで普通のアロンアルファを使ってもかまいませんがものすごく強靭なガードになってしまうのでご注意。液状の場合毛細管現象化なにかでブラシを伝って上まで上がってきてしまうのでガチガチのガードが誕生します。バスのバイトまでガードするスーパーガードになりかねません。

このあとフットボールも自作しました。今回はきちんとヘッドの根元に巻いたので先ほどよりも見栄えがよろしい(笑)しかしここでも問題が・・・

裏側にラバーを巻かずに表に乗せ続けていた為裏側がスカスカ・・・。ジグヘッドの上に乗っけるだけじゃなくて下側にも巻いてあげないとこうなります。しかもスレッドの固定で接着剤つけすぎたのもありかなり不自然な感じ。
とはいえ、全体を見ればそれなりに雰囲気はあるので概ね成功といえるでしょう。こうして人は成長していくわけです。次回はスモラバ偏をお送りします!?
総投資・・・9094円、総製作・・・3個、単価・・・3031円。たっけ!

スモラバとラバジどちらから先に作成するか悩みましたが、なんとなく多少失敗してもごまかしがききそうなのでラバジから作ることに決めました弱腰な僕。出る前から負ける事考える馬鹿いるかよ!(by猪木)

まずは準備から。バイスを机に固定します。ちなみにバイスってのは万力のことですから専用の物じゃなくても大丈夫ですが専用を使ったほうが気分出るので安いのでいいから買いましょう。2000円弱です。

さらにボビンホルダーにボビンをくっつけて糸を出しておきます。はさむのは見たまんま普通にはさんでもらってスレッド(糸)は先端の筒から出しておきます。糸を簡単に出す為にスレッダーとかいう道具も出てるようですが買って使うほど難しい作業でもないので必要なし。不器用度に自信のある人は買っておきましょう。

バイスにジグヘッドをはさみます。今回はコブラヘッドを使います。僕はフックを下向きに挟んでみましたが向きはどっちでもいいんじゃないでしょうか?お好みでどうぞ。下手な挟み方をすると作業中にジグヘッドが飛んで来ることになるのでしっかりはさんで動かないか確認しておきましょう。
その後にスレッドで下巻きをしておきます。これをやっておくと後半でラバーを巻いたときにずれにくいはずです。面倒なら飛ばしてしまってもいいでしょう。このへんは自作の良さ売り物じゃないから気分次第で適当に行きましょう。


使いたいカラーのラバーを10cmくらいに切って2~4枚用意してそれを半分に裂いておきます。縦の切れ目が入っていますから手で簡単に裂けます。僕は黒2枚、茶1枚を半分に裂いたので6枚あります。完成後のボリュームが変わってきますのでこのあたりの量もお好みでどうぞ。

続いてラバーをジグヘッドに巻いていきます。ジグヘッドの先ほど下巻きをしたところにラバーの中央がくるように乗っけてスレッドで巻いていきます。このあたりきつめに巻いていかないと出来上がりがぶちゃいくになるばかりかラバーがずれてとんでもないことになるのでしっかり締めこんでいきましょう。1枚乗っけるたびに1~2周きっちり締めこめば十分でしょう。あんまり巻きすぎてもかさばってうまく仕上がりませんから注意。
乗っけていくラバーの色の順番で仕上がり時の見え方が違うのでこのあたりにセンスが出るといえます。

で、全てのラバーを巻き終わったらしっかりとスレッドで締めこんだ後接着剤でスレッドがほどけないようにとめてしまいます。接着剤の量に最新の注意を払わないとうまく広がりませんので慎重に。そしたらラバーを全部フック側に追いやります。普通に追いやればいい感じになると思いますが言うことを聞かない場合は追いやった後にスレッドで一巻きしてとめちゃいましょう。自作ですからそれもアリです。
作業も残すところ後少し頑張っていきましょう。


ラバーを1片ずつつまんで引っ張ります。そしてはさみを使って端からゆっくりと切っていきます。しっかり引っ張っていれば面白いようにパラパラばらけていきます。それを全てのラバー片に行っていきます。僕は6枚使ったので6回やるわけですね。
全て切り終わったらざっと確認して全てのラバーがばらけているかを確認してください。中にはガッツでくっついたままの部分があります気合が入ったラバーです。そのままというのも味がありますが最初くらいはしっかり全部のラバーにばらけてもらいましょう。

完成です。この後全体のラバーの長さを好みの長さになるまで刈り込んで仕上げです。

はい、僕の自作ラバージグ第一号ですが余裕の失敗です。根元にラバーを巻かなくてはいけないのに楽勝で1段先のワームキーパーに巻いています(笑)途中で気がつきましたが後戻りはできません過酷な旅路。
 このあとフックガードのブラシを必要な人はくっつけます。ゼリー状の瞬間接着剤で穴に固定してください。
このあとフックガードのブラシを必要な人はくっつけます。ゼリー状の瞬間接着剤で穴に固定してください。この接着剤は必ずゼリー状のものにすること。これは絶対です。とはいえ、自作なんで普通のアロンアルファを使ってもかまいませんがものすごく強靭なガードになってしまうのでご注意。液状の場合毛細管現象化なにかでブラシを伝って上まで上がってきてしまうのでガチガチのガードが誕生します。バスのバイトまでガードするスーパーガードになりかねません。

このあとフットボールも自作しました。今回はきちんとヘッドの根元に巻いたので先ほどよりも見栄えがよろしい(笑)しかしここでも問題が・・・

裏側にラバーを巻かずに表に乗せ続けていた為裏側がスカスカ・・・。ジグヘッドの上に乗っけるだけじゃなくて下側にも巻いてあげないとこうなります。しかもスレッドの固定で接着剤つけすぎたのもありかなり不自然な感じ。

とはいえ、全体を見ればそれなりに雰囲気はあるので概ね成功といえるでしょう。こうして人は成長していくわけです。次回はスモラバ偏をお送りします!?
総投資・・・9094円、総製作・・・3個、単価・・・3031円。たっけ!